はじめに
読書感想文は、読んだ本の内容や感想を自分の言葉で表現することで、読解力や表現力を高める学習活動です。しかし、最近では、AI(人工知能)を使って読書感想文を作成するという方法が話題になっています。AIに質問するだけで自然で説得力のある文章が返ってくるという便利さから、読書感想文やリポートなども簡単に作成できてしまうのです¹²。
AIで読書感想文を作成するとどうなるか
AIで読書感想文を作成するという方法は、一見すると手間が省けて楽になるように見えますが、実際には学習への悪影響が大きいと考えられます。その理由は以下の通りです。
- 読書感想文の目的が失われる:読書感想文は、本を読んで自分なりに考えたり感じたりしたことを文章にすることで、本の内容やメッセージを深く理解したり、自分の考えや感情を表現したりする力を育てることが目的です³。しかし、AIに任せてしまうと、本を読むことも考えることもしなくなってしまい、読書感想文の目的が失われてしまいます。
- 盗作や不適切な引用のリスクが高まる:AIは、インターネット上の膨大なデータから文章を生成しますが、その中には他人の著作物や個人情報なども含まれている可能性があります。そのため、AIが生成した文章をそのまま使うと、盗作や不適切な引用のリスクが高まります。実際に、イタリアでは、個人情報の保護に関する法律に違反している疑いがあるとして、一時的に使用を禁止すると発表するなど、規制に向けた動きが出始めています²。
- AIの文章に騙される危険性がある:AIは、人間が書いたような自然な文章で回答してくれますが、それは必ずしも正しいとは限りません。AIは、データから学習したパターンや統計的な確率で文章を生成しますが、その中には誤った情報や偏った見解も含まれている可能性があります。そのため、AIの文章に騙される危険性があります。
AIで読書感想文を作成するのを防ぐには
AIで読書感想文を作成するのを防ぐには、以下のような対策が考えられます。
- 読書感想文の目的や意義を教える:読書感想文は、ただ単に課題をこなすためにやるものではなく、自分の力を高めるためにやるものだということを教えることが大切です。読書感想文の目的や意義を理解させることで、AIに頼らずに自分で考えて書く姿勢を育てることができます。
- 応募要項や審査基準を明確にする:読書感想文コンクールなどに応募する場合は、応募要項や審査基準を明確にすることが重要です。AIを使った盗作や不適切な引用があった場合には、審査の対象外となり、事実上の失格となることを明記することで、AIの悪用を抑止することができます³。
- AIの文章の特徴や問題点を教える:AIの文章は、人間が書いた文章とは違う特徴や問題点があります。例えば、文章の構成や論理性が弱かったり、表現が矛盾したり、情報源が不明確だったりします。AIの文章の特徴や問題点を教えることで、AIの文章に騙されないようにすることができます。
まとめ
読書感想文をAIで書くという方法は、学習への悪影響が大きいと考えられます。そのため、読書感想文の目的や意義を教えたり、応募要項や審査基準を明確にしたり、AIの文章の特徴や問題点を教えたりするなどの対策が必要です。AIは、学習の補助ツールとして使う分には有用ですが、学習そのものを代行させることは避けるべきです。
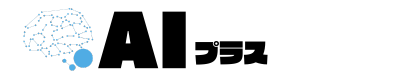
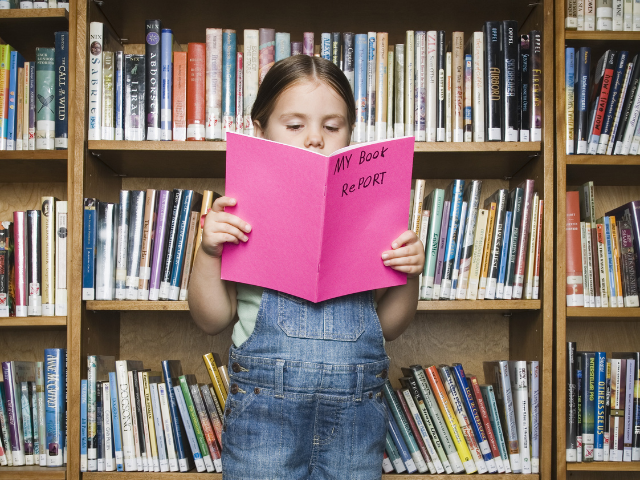


コメント